先日令和6年のネットワークスペシャリストの試験を受験してきました。実際に受験してみて、この試験を受験するべきなのかどうかを書いていきます。
私の経歴と受験した理由
まず私の経歴ですが、30代前半で営業職から未経験のインフラエンジニア職に転職し、複数企業のネットワークの運用業務を2年、企業の業務システムの運用業務を1年ほど経験してきました。
業務システムの運用ではネットワークに関する業務は多くないので、実質ネットワークに関する業務の経験は2年ほどとなります。
インフラエンジニアに転職してからの最初の現場がネットワークの案件だったこともありネットワークに面白みを感じていたのですが、現在の案件がネットワークの業務が少ないため、このままではネットワークの知識を忘れてしまう!と思い、ネットワークスペシャリスト試験の受験に至りました。
結論
ネットワークスペシャリスト試験を受験するべきなのかの結論を言うと、ネットワークの知識をこれからつけていきたいという方や若手のエンジニアの方は、
絶対に受けるべきです!!めちゃくちゃおすすめです!!!
なぜ受験した方が良いのかということは後述しますが、個人的にはここまで受験したほうが良い、身になったと思える資格試験は中々ないのではないかという印象です。さすが国家資格。
インターネットで「ネットワークスペシャリスト」で検索をすると、候補に「意味ない」といったワードが出てくるため、取得しても意味がないといった意見や、意味があるのか?と思っているかたもいるのかと思いますが、全く意味はなくないと思います。
合格率が15%前後と中々難関な試験ですが、ぜひがんばって勉強して受験し取得をめざしましょう!
【感想】午前Ⅰ
午前Ⅰの試験は応用情報技術者試験の問題から出題されますが、勉強の段階で全く理解が出来ず、以下のサイトを参考にさせて頂き、過去6回分の問題を全て記憶する手法で挑みました。
その結果、自己採点をしたところなんと2問正解が足りておらず、午前Ⅰを突破することが出来ませんでした・・・
こちらのサイトでは過去6回分の問題から12、3問出題されるとありましたが、7、8問しか出題がされず悔しい結果となりました。
もちろんその年によって過去問から使われる数も違うため、運が悪かったと思うしかないかなと思います。
ただ、問題を丸暗記しただけですが初見の問題でも何となく解けるようになったので、プラスαで応用情報の問題をすこし勉強しておけば突破できるかもといった所感でした。
【感想】午前Ⅱ
午前Ⅱの試験対策は、以下のサイトを使わせていただきました。
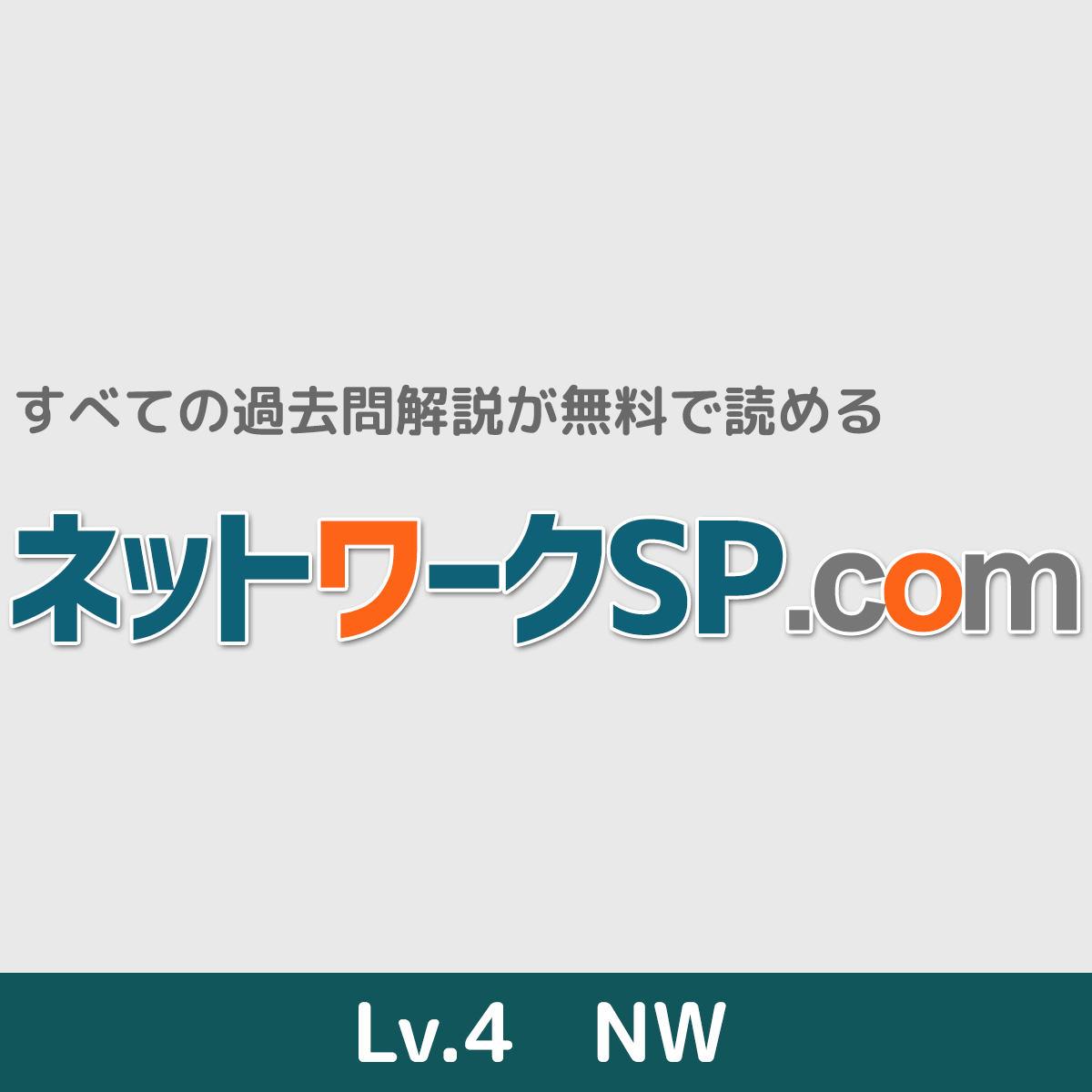
試験の4ヶ月以上前から通勤などの移動時はスマホで問題を解くようにし、掲載されている問題を90%近く正解できるまでやり込みました。
結果、25問中20問正解することができ、午前Ⅰを突破できていれば・・・と悔やまれるばかりです。
問題は過去問からの出題も多くあった上に、ネットワークの知識は午後試験の勉強でしているため、初見の問題があっても難なく解くことができたという印象です。
そのため、過去問道場以外は午前Ⅱ対策の勉強はする必要はないと思います。
【感想】午後Ⅰ
午後Ⅰの試験は、それぞれ以下について問われました。
- 問1・・・CDNにおけるBGPでの通信
- 問2・・・SD-WAN
- 問3・・・IPsecとPACファイル
最初に各問をざっとみて、SD-WANについての知識が怪しかったので問1、3を選択することにしました。
どちらもそこまで難しいことは問われておらず、記述問題も過去問で同じような内容があったりしたため、空欄はなくしっかりと解答することが出来ました。(例えばサーバの監視をHTTPではなくICMPでのみ行った場合の問題など)
今回は午前Ⅰが通過できなかったため午後試験は採点されませんが、6割以上は正解できたのではないかといった所感です。
なお、午後試験の対策は以下のネスペシリーズをメインに使用させていただきました。
こちらは色々なサイトでおすすめされていますが、その情報に偽りなく、本当におすすめの参考書です。
単純な問題や解答の解説だけでなく、以下のような記述式問題の書き方についても書いてあり、試験の際に非常に助かりました。
- 解答は問題文の言い回しや文言を使って書く
- 自分が知らない知識を問われた場合でも、問題文を読み込むことで解答が導き出せる可能性がある
- 問いに対して、間接的な結果ではなく直接的な結果を記載する
午後Ⅱ試験でも言えることですが、過去問で問題の解き方や長文に慣れ、あとは参考書やインターネットで足りない知識を補填していくのが勉強法かと思います。
このとき重要なのは、例えばIPsecにはトランスポートモードとトンネルモードがありますが、それぞれのモードの違いだけでなくそれぞれのモードが使用されるのはどんな場面なのか、なぜ違うモードがあるのか、といった、実際にその技術が使われるとどうなるのかといったところまで理解しておくことです。
すでにエンジニアとして業務をおこなっている方は、その業務で関わっているシステムのネットワークについて調べると、よりネットワークスペシャリスト試験で問われる内容についての理解を深められるかと思います。
【感想】午後Ⅱ
午後Ⅱの試験は、それぞれ以下について問われました。
- 問1・・・VXLANを利用したデータセンターのネットワーク
- 問2・・・メールのセキュリティ対策
ひと目見て問1の方が難しそう(VXLANとかVTEPとかあんま知らん・・・)と思い、問2を選択し解答していたのですが、序盤でわからない部分があり15分くらい経過してから問1に切り替えて解答しました。
結果、やはり難しかった・・・のですが、前日にたまたまVXLANについて軽く勉強していたことと、分からない部分は問題文から解答を導き出す手法でなんとかほぼほぼ解答欄を埋めることは出来ました。
VXLANについては過去10年分くらいの試験にも出題されていなかったかと思うので、やはり出題範囲の技術は隅々まで勉強し、完全でなくとも大方は理解しておく必要があるなと感じました。
また、問2は情報処理安全確保支援士の問題のようだったという声も多くあったようで、セキュリティに強い方であれば簡単な問題だったようですが、DKIMについて勉強が足りていなかったと思い避けてしまっていました。
午後Ⅰで出題されたSD-WANや送信ドメイン認証など、今現在の企業のネットワークで使われることが多くなっている技術についてはより重点的に勉強しておく必要があると実感しました。
受験するべき理由
先に結論として、絶対に受験するべき!!!とお伝えしていましたが、私がそう考える理由として以下があります。
『企業のネットワークを想定した試験問題であるため、実践的な知識が身に付く』
この問題の形式であることで、通信の流れやなぜその技術が必要なのかまで理解しておく必要があるため、実際の業務でも活きる場面が非常に沢山ありました。
例えば、私はDNSについてゾーンファイルのDNSレコードの知識はなんとなくありましたが、DNSサーバには種類があって、どんなときにどのDNSサーバに名前解決の要求がされるのか、といった知識はありませんでした。
実際に業務でDNSレコードを変更する作業が発生したのですが、DNSサーバには内部DNSサーバと外部DNSサーバ、キャッシュDNSサーバがあり、以前までの知識ではどこに設定をすれば良いのか、また設定をするとどう変わるのか、といったところまでは理解が出来ていませんでした。
しかしネットワークスペシャリスト試験の勉強をしてからは、通信の流れやDNSレコードを変えることで何が変わるのかといったことまでしっかり理解できるようになったため、どのDNSサーバに設定をする必要があるのか、なぜそのサーバだけで良いのかといったことまで他の人に説明できるまでになりました。
ネットワークは通信の仕組みさえ理解してしまえば割と簡単(とは言っても色々な技術があるから難しい・・・)だと思いますが、その仕組みを理解することが大変だと思っています。
仕組みを理解するために最適なのは、実際に稼働しているネットワークに触れることだと思いますが、中々触れられる状況にない方も多いかと思います。
そこでこのネットワークスペシャリスト試験の登場です。
試験で出題される問題のネットワークは実際の企業のネットワークに比べて規模は小さいですが、通信の仕組みを理解するには十分です。
この試験の合格を目指して勉強するだけでも、ネットワークについての話は相当できるようになると思います。
以上のことから、これからネットワークの知識を付けたいという方にはネットワークスペシャリスト試験の受験を強くおすすめします!!
私も今年の試験は合格できませんでしたが、まずは午前Ⅰの免除のために秋の高度試験を受験し、必ず来年の試験には合格したいと思います。
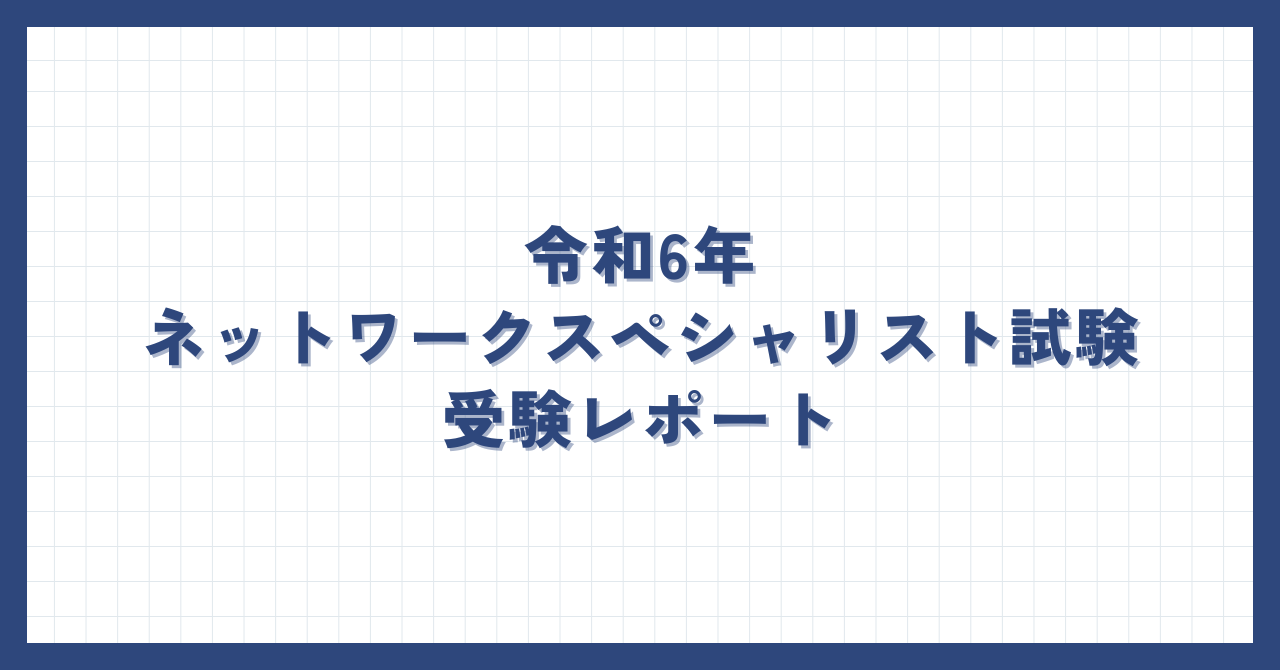


コメント